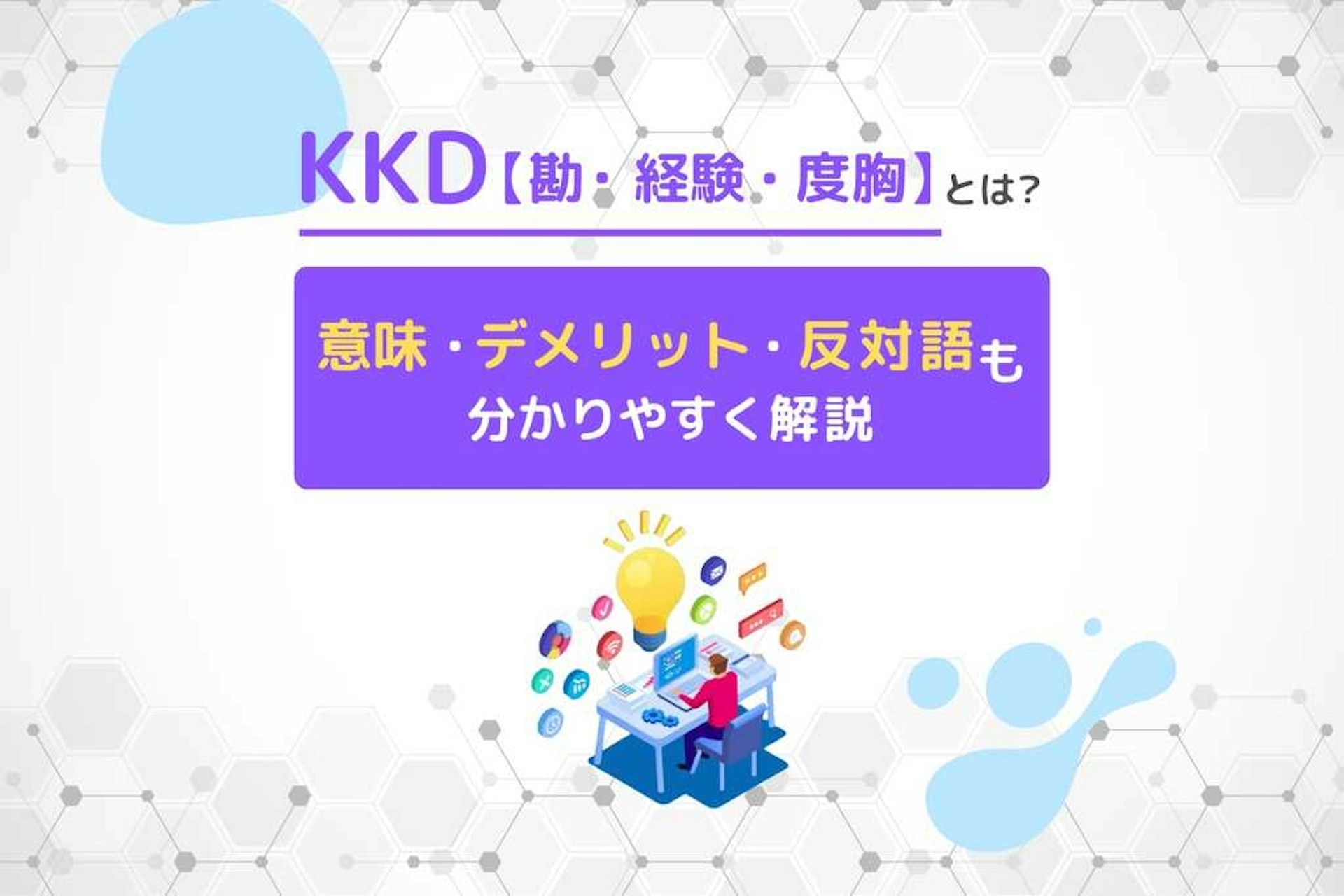「KKD(勘・経験・度胸)」という言葉を耳にしたことはあるものの、正確な意味や使われ方を把握できていないという方もいるのではないでしょうか。属人的な判断に頼るこの手法は、再現性やデータ活用の観点から見直されてきましたが、一定のメリットもあります。
この記事では、KKDの意味や具体的な使われ方、メリットやデメリットについて解説します。さらに、KKDの反対語として注目される「データドリブンマーケティング」についても解説します。
KKD(勘・経験・度胸)とは?
KKD経営が行われてきた背景
KKD法とは?
KKDのメリット・デメリット
KKDの反対語:DDM(データドリブンマーケティング)
まとめ|KKDとDDM、自社に合った選択が重要
KKD(勘・経験・度胸)とは?
KKDは「経験(Keiken)」「勘(Kan)」「度胸(Dokyo)」の頭文字を組み合わせた言葉で、主に日本のビジネス現場で使われてきた意思決定のスタイルを指します。
過去の経験や直感を頼りに、明確なデータや根拠がないまま判断を下すことが特徴です。特にスピードが求められる場面では、複雑な過程を省いて即断するために用いられることがあります。
感覚的な判断に偏ると、客観性に欠けるため重要な選択肢を見落とすリスクも伴いますが、データでは読み取れない部分を補完できることもあります。KKDはデータと併用することで、効果を発揮するでしょう。
▶︎あわせて読みたい:大規模なパーソナライゼーション戦略: KKD(経験・勘・度胸)に頼らない消費者調査
KKD経営が行われてきた背景
KKDは日本のビジネス界で長く重視されてきました。ITやAI技術が発達していなかった時代は活用できるデータが限られていたため、経験や勘に頼らざるを得ない環境だったことが背景として挙げられます。特に日本の製造業では、職人の技術が現場経験として重宝される文化であったことも要因でしょう。実際に創業者のなかには、即断即決で企業を成功に導いてきた人が多くいます。
現代はITやAI技術の発展により、大量のデータ分析が可能になりました。インターネットが普及したことで顧客ニーズが多様化し、個人の感覚だけではビジネスの方向が予測できない時代に突入しています。一方で、KKDの効果が見直されている一面もあります。多様なニーズに応えるには、データから読み取れない新たな発想も必要です。
KKD法とは?
KKD法は、KKDに基づいてプロジェクトの工数(作業にかかる労力や時間)を見積もる方法です。特にIT業界では、開発経験のある担当者が感覚的に判断する場面が多く見られました。
KKD法は判断基準が人によって異なることが課題とされていますが、決断のスピードを重視する現場では有効です。また、データに基づいたフレームワークでも入力値の選定や評価には主観が入り込む余地があるため、KKD法を意識することはデータの客観性を測る際にも役立つといえるでしょう。
KKD法以外のフレームワーク
KKD法以外にも、工数や作業量を見積もるためのフレームワークは複数存在します。代表的なものにLOC法、ファンクションポイント法、COCOMO法があり、いずれも数値や過去のデータをもとに算出する設計です。これらは属人的な判断を避け、一定の基準に基づいて見積もりを行うことを目的としています。
LOC法
LOC法は「Lines of Code」の略で、ソフトウェアのソースコード行数をもとに開発規模を見積もる方法です。開発現場では古くから使われています。ウォルター・J・ロマノフ氏によって提唱され、1970年代から始まりました。
デメリットはソースコード行数のみでは開発者のスキルなどが考慮されず、品質を正確に知ることが困難なことです。使用言語によっても値が異なります。
ファンクションポイント法
ファンクションポイント法は、ユーザーから見た機能の数と、各機能の複雑さを基準に開発規模や工数を見積もる方法です。画面入力や出力、データファイルなどを分析し、それぞれの難易度を点数化して合計したもの(ファンクションポイント)を用います。1979年にIBM社のアラン・J・アルブレヒト氏によって提唱されました。
コード量ではなく機能数を基準に評価するため、使用するプログラミング言語に影響されないことが大きな利点です。また、要件が完全に固まっていなくても、ある程度の機能が見えていれば概算できるため、初期段階での見積もりにも適しています。正確な計算には分析力が必要です。
COCOMO法
COCOMO(ココモ)法は「Constructive Cost Model」の略称で、ソフトウェア開発における工数や期間を統計的に見積もる手法です。ソースコードの行数、開発者のスキル、開発規模、制約条件などをもとに算出します。1981年にTRW社のバリー・ベーム氏によって提唱されて以来、改良が重ねられてきました。
シンプルな計算式により、専門知識がなくても活用できるのが特徴です。また、複数の計算モデルがあるため、目的による使い分けもできます。
KKDのメリット・デメリット
KKDには迅速な判断を可能にする利点がある一方で、客観的な裏づけが乏しく、再現性に欠けるといった課題も存在します。メリットとデメリットの両面からKKDを整理し、活用のポイントを考えていきましょう。
メリット
KKDの最大の強みは、過去の経験や直感を活かし、スピーディーに意思決定できる点にあります。ここでは、ビジネス現場で実際に役立つ3つのメリットを紹介します。
意思決定のスピードが速い
KKD法の大きな利点は、意思決定のスピードが格段に速くなる点です。特に、顧客からのクレームやシステム障害が発生した緊急の場合に、迅速に対応できます。すべての業務に適しているわけではありませんが、時間的制約がある場面では強力な武器になるでしょう。
データがない領域で勘や経験を応用できる
参考となるデータが十分に揃っていない状況では、過去の経験や勘に頼ることで、意思決定につなげられることがあります。前例のない事業を起こす場合はデータがないため、他の事業経験などに基づいたKKDが必要なこともあるでしょう。また、採用において「好印象かどうか」というデータ化しづらい基準を用いる場合も、KKDは応用できます。
クリエイティブな業務に役立つ
KKDは、創造性が求められる業務で特に効果を発揮します。広告制作や商品開発、デザインなどの分野では、数値だけでは測れない顧客の感情やトレンドを捉えることで、企画した商品やキャンペーンがヒットすることもあります。データを参考にしない分、実行に移すには度胸も必要となるでしょう。KKDの活用は独自性のあるアイデアを生み、革新的な成果につながる可能性を秘めています。
デメリット
KKDには即断力や柔軟性といった利点がある一方で、運用には注意が必要です。属人的な判断に依存するため、組織全体での安定運用や継続的な成果につなげるには限界があります。ここでは代表的なデメリットを解説します。
経験のある人材でないと活用できない
KKDは誰でも使える手法ではありません。新入社員や未経験者に、経験に基づいた判断をベテランと同じように求めるのは現実的ではなく、結果に差が出るのは自然なことです。勘や度胸も、経験に裏打ちされてこそ力が発揮できるでしょう。KKDを活用するには、ある程度の経験がなければなりません。
ノウハウが蓄積されない
KKDは個人の経験や勘に依存するため、組織としてノウハウを蓄積しづらいという課題があります。たとえ優秀な社員が成果を出していても、その判断プロセスが言語化されていなければ、他のメンバーが再現することは困難です。業務の引き継ぎにも支障が出るでしょう。継続的に成果を出すためには、経験を言語化して共有し、会社の仕組みとして残す工夫が必要です。
客観的な判断ができない
KKDはデータに基づかず主観的になりがちなため、誤った判断を引き起こしかねません。特に近年はインターネットの普及により、顧客のニーズは多様化しており、経験だけでは幅広いニーズを把握しきれません。現在のマーケティング戦略には、多角的な分析による判断が必要とされています。
KKDの反対語:DDM(データドリブンマーケティング)
KKDが経験や勘に基づく意思決定法であるのに対し、DDM(データドリブンマーケティング)はデータの分析結果に基づいて意思決定を行うマーケティングです。
データドリブンマーケティングを成功に導くには、目標値を立てることが大切です。目標値が決まると、どのようなデータを集め、どう分析するかも決まります。社内でデータ収集と分析の重要性を浸透させることも、データ活用をスムーズにするでしょう。
▶︎あわせて読みたい:データドリブンマーケティングとは?実行の手順や成功に導くポイントを解説
▶︎あわせて読みたい:データドリブン経営とは?取り組むメリットや進め方、成功事例を解説
データドリブンが注目される理由
データドリブンが注目される背景には、パーソナライズの重要性が高まったことと、AI技術の発展があります。インターネットの普及により情報収集の手段が広がるとともに、利用できる商品やサービスの選択肢も増えました。こうした状況下では、パーソナライズされたアプローチが顧客の選択を左右します。AI技術が発達したことで、顧客の好みや行動傾向のデータ分析がスピーディーになり、パーソナライズも手軽かつ精密にできるようになりました。
近年では71%の消費者がブランドによるパーソナライズされたサービスを期待しているという調査結果(2021年)も出ています。個々のニーズに応えるには、主観に頼るKKDでは対応しきれません。DDMはパーソナライズされた体験を提供する手段として注目されています。
参考:Meltwater 大規模なパーソナライゼーション戦略 KKD(経験・勘・度胸) に頼らない消費者調査
▶︎あわせて読みたい:データドリブンとは?メリットや取り組むポイントをわかりやすく解説
DDMへの移行にはツールの活用が効果的
データドリブンマーケティングを実践するには、データを正確に収集・分析できるツールの導入が重要です。代表的なものとしては、以下のようなものがあります。
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Web解析ツール | Webサイトの訪問経路や滞在時間を可視化できる |
| BI(ビジネスインテリジェンス)ツール | 売上や顧客動向など企業が抱える膨大なデータを分析することで意思決定につなげる |
| SFA(営業支援システム)ツール | 商談状況やスケジュールを管理することで、営業活動をサポートする |
| DMP(データマネジメントプラットフォーム) | サーバーに保存された情報を一元化し、顧客データを管理する |
ツールを導入する際は、費用以外に、他のツールと連携ができるか、社員が使いやすいかどうか、サポート体制があるかどうかも確認しておきましょう。
▶︎あわせて読みたい:消費者インサイトとは?事例や調査方法、活用のポイントを解説
▶︎あわせて読みたい:セールステックとは?カオスマップで市場と主要7カテゴリを解説
まとめ|KKDとDDM、自社に合った選択が重要
KKDは経験や勘を活かした迅速な判断が可能で、特に現場対応や創造的な業務に強みを発揮します。一方、DDM(データドリブンマーケティング)は、蓄積されたデータをもとに客観的かつ再現性のある意思決定を行う手法です。
顧客ニーズの多様化や市場変化のスピードが増す現代においては、DDMの重要性が高まっています。しかし、すべてをデータで割り切れるわけではなく、状況によってはKKDの柔軟性が有効な場面もあります。両者の特性を理解し、自社の業務内容や組織体制に応じて適切に使い分けることが、持続的な成果と競争力の確保につながるでしょう。
この記事の監修者:
宮崎桃(Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター)
国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム