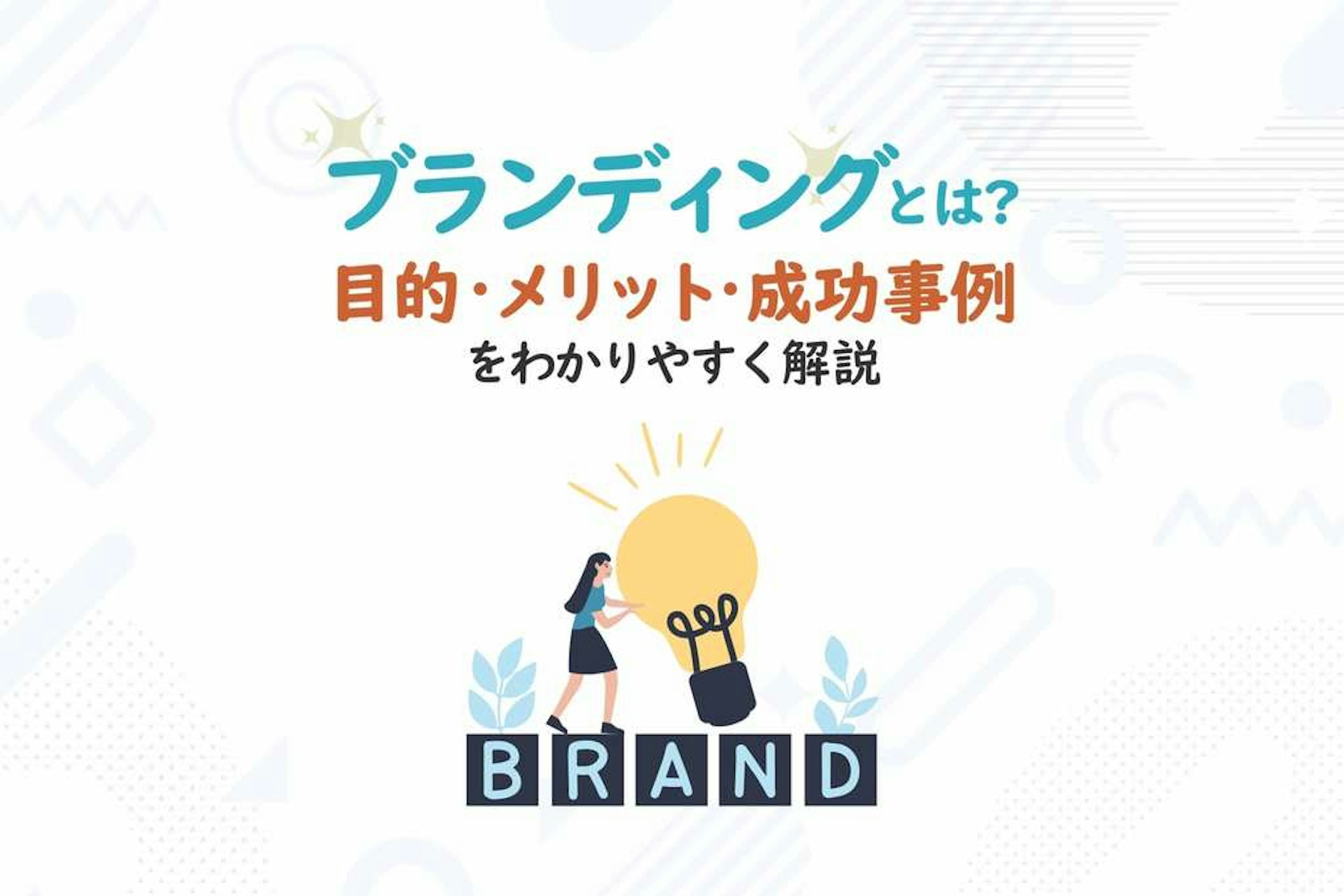現代は激しい競争環境の中で、多くの企業が「どうすれば顧客に選ばれるのか」という悩みを抱えています。特に中小企業にとって、限られたリソースで他社との差別化を図ることは大きな課題です。
そこで重要になるのがブランディングです。ブランディングとは、自社を顧客にとって特別な存在として印象づけ、価格競争から脱却して選ばれる企業になるための戦略です。
本記事では、ブランディングの定義やメリット、具体的な実行手順を詳しく解説します。資生堂やコカ・コーラなど成功企業の事例も紹介します。
ブランディングとは?
ブランディングのメリット3つ
ブランディングの種類
ブランディングを実行する手順
ブランディングを成功に導くポイント3つ
ブランディングの企業成功事例3つ
まとめ|ブランディングで顧客に選ばれる存在になろう
ブランディングとは?
ブランディングとは、自社の商品やサービス、もしくは自社そのものを顧客に「特別なもの」として印象づけ、競合他社との違いを明確にする活動のことです。自社のコンセプトに基づき、ロゴやデザインを工夫したり、会社を立ち上げたきっかけを紹介したり、社会課題に関わったりすることなどが活動の例として挙げられます。
ブランディングにより自社のブランド価値が高まれば、広告に頼らなくても価値を維持できるようになります。また、価格の安さで勝負する必要もありません。顧客から信頼されるブランドになれば、長期的なニーズが期待できるでしょう。
ブランディングの目的
ブランディングの主な目的は以下の3つです。
- 市場での競争優位性の確立
- 顧客との信頼関係の構築
- 顧客の購買意欲の向上
ブランドを唯一無二の価値あるものとして押し上げることで、他の類似商品との違いが明確になり、購買意欲を高めることができます。顧客が商品・サービスを実際に体験し、イメージ通りの価値があるとわかれば、ブランドに対する信頼が生まれてリピートにつながるでしょう。
ブランドを作る要素
ブランドとは、他の企業や商品・サービスと区別するために、ある企業や商品・サービスを定義づけるものです。ブランディングとはブランドを作り上げることとも言えるでしょう。ブランドを作る要素と具体例を紹介します。
| ブランドを作る要素 | 具体例 |
|---|---|
| ブランド名 | Meltwater |
| ブランドロゴ | |
| ブランドカラー | ティールブルー |
| ブランドメッセージ | Outside Insight |
| ミッション | 常に革新を続け、最高水準のサービスと持続可能な成長を提供する |
| 開発国 | ノルウェー (現在の本社はアメリカ) |
ブランドの要素は一貫性が大切です。ブランドロゴ、ブランドカラー、ブランドメッセージなどがリンクしていると互いが強調され、見た人に印象づけることができます。国もブランドイメージに影響します。上記のほかに、キャラクターや音楽、空間デザイン、パッケージデザインなどもブランドを作る要素です。
マーケティング、プロモーションとの違い
ブランディングと混同されやすい概念に、マーケティングとプロモーションがあります。それぞれ別のものですが、互いに密接に関わり合っています。
マーケティングとは、商品やサービスが売れる仕組みを作ることで、ブランディングとプロモーションはその仕組みの中の活動の一つとして位置づけられます。
ブランディングが他社と違ったブランドの価値を作り出す活動である一方、プロモーションは広告や展示会などを通じて商品の認知度向上や販売促進を図る活動です。ブランディングにより商品・サービスの訴求ポイントがわかりやすくなるため、プロモーションがスムーズになります。ブランディングが顧客に一定のブランドイメージを形成する長期的な取り組みであるのに対し、プロモーションは短期的な取り組みです。
ブランディングのメリット3つ
ブランディングのメリットとして以下の3つが挙げられます。
- 競合商品・サービスと差別化
- 広告費用の削減
- 長期的な信頼とロイヤリティの獲得
競合商品・サービスと差別化
ブランディングは、自社の商品・サービスを競合他社と差別化するための有効な手段です。差別化に成功したブランドは、価格競争に巻き込まれることなく、顧客からの支持を獲得し、安定した売上を維持できます。
機能性を高めたりデザインやロゴを変えたりする他、ブランドストーリー(ブランドの価値を伝えるコンテンツ)などで自社独自の価値観を打ち出すことで、顧客に強い印象を残せるでしょう。
▶あわせて読みたい:ブランド・エクイティとは?構成要素や測定方法、具体例を解説
広告費用の削減
信頼性の高いブランドを築き上げることで、広告宣伝費を大幅に削減できる可能性があります。顧客のブランドロイヤリティ(ブランドへの愛着)が高まれば、口コミや評判によって自然と認知度が向上するからです。
新商品やイベントなどの情報を顧客が自発的に発信することで、広告費用対効果を最大化した効率的なマーケティングを展開できます。
長期的な信頼とロイヤリティの獲得
ブランディングによって、顧客からの長期的な信頼とロイヤリティを獲得できます。継続的にブランドの価値を伝えることで、顧客が「この会社なら間違いない」と信頼してくれるようになります。
長期的な信頼が築かれると、顧客はブランドのファンとなり、ロイヤルユーザーへと変化していきます。ロイヤルユーザーはリピート購入を積極的に行い、一般顧客と比べて購買単価も高くなる傾向があります。企業の安定した収益基盤となるでしょう。
▶︎あわせて読みたい:ブランドロイヤリティとは?高めるメリットや評価指標、事例を解説
ブランディングの種類
ブランディングは社内と社外に向けて行われます。社内で従業員がブランドの価値を理解し、体現できるようになれば、社外に向けたブランディングの効果も高まるでしょう。
▶あわせて読みたい:コーポレートブランディングとは?目的や進め方、成功事例を解説
インナーブランディング
インナーブランディングとは、従業員に向けて行うブランディングのことを指します。社内研修や勉強会を通じて、企業の理念や価値観を従業員に浸透させるのが代表的な取り組みです。
インナーブランディングの目的は、従業員一人一人が自社のブランドに対する理解を深め、ブランドの価値観を共有することです。これにより、従業員はブランドの代表者として、お客様に対して一貫したブランド体験を提供できるようになります。
アウターブランディング
アウターブランディングとは、顧客や取引先など、社外のステークホルダーに向けて行うブランディングのことです。「ブランディング」というと、アウターブランディングを指すことが一般的です。広告やパッケージデザインを工夫したり、求人の応募先としての会社の魅力を打ち出したりするなど、様々な施策が含まれます。
アウターブランディングの目的は、ブランドの認知度を高め、ブランドイメージを確立することです。これにより、顧客や求職者からの信頼を獲得すれば、売上や採用に好循環をもたらします。
商品・事業ブランディング
商品・事業ブランディングとは、特定の商品や事業が市場で選ばれ続けるために行うアウターブランディングのことです。商品そのものの価値や魅力を顧客に効果的に伝えることで、競合商品との差別化を図ります。
具体的な取り組みとしては、商品のキャッチコピーの考案やパッケージデザインの作成、価格設定の最適化などが挙げられます。また、既存商品の名称やデザインを見直す「リブランディング」も、商品・事業ブランディングの一環として多くの企業で実施されています。
採用ブランディング
採用ブランディングとは、求職者に対して自社の魅力を効果的に伝え、働く場所として選んでもらうためのアウターブランディングのことです。現代では多くの企業が人材確保に苦労しており、給与や待遇だけでは優秀な人材を獲得できなくなっています。そのため、会社のビジョンや働きがい、職場の雰囲気といった独自の価値を明確に発信することが重要です。
具体的な方法としては、採用サイトに社員インタビューを掲載したり、SNSで社員の日常を発信したりすることなどが挙げられます。採用ブランディングに成功すれば、自社の求める人材を獲得しやすくなります。
ブランディングを実行する手順
ブランディングを実施する手順を解説します。
1. 現状分析を行う
まずは、自社の現状を客観的に把握することから始めます。分析に役立つ代表的なフレームワークは以下の通りです。
| フレームワーク | 概要 |
|---|---|
| 3C分析 | 自社(Company)、顧客(Customer)、競合(Competitor)の3つの視点から分析 |
| SWOT分析 | 自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を分析 |
| PEST分析 | 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の観点から外部環境を分析 |
| STP分析 | セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)の3つを分析 |
| 5フォース分析 | 新規参入の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力、代替品の脅威、業界内の競合の5つの力を分析 |
これらのフレームワークを活用することで、ターゲット層の選定から、自社の強みを活かし、弱みを補う戦略まで立てられます。現状分析の結果は、ブランディング戦略の基盤となる重要な情報です。
2. ブランドの提供価値を設定する
ブランドの提供価値とは、ブランドから得られる顧客側のメリットのことです。具体的には、以下のような価値を指します。
- 機能的価値(品質、性能など)
- 情緒的価値(効果の実感、商品に関わる体験など)
- 自己表現的価値(ステータス、所属感など)
- 社会的価値(企業活動に社会的な意義が感じられるなど)
ブランドの提供価値は、ターゲット顧客のニーズに合致するものでなければなりません。また、複数の価値を提供する場合は関連性があるとよいでしょう。
例えば、アウトドアウェアを販売する「パタゴニア」は、高品質なアウトドア用品という機能的価値に加え、環境保護という社会的価値を提供しています。アウトドアが好きな人は、自然環境に親しみを持っていることが多いです。関連性のある付加価値により、顧客を引きつけていると言えます。
▶︎あわせて読みたい:情緒的価値とは?機能的価値との違いやブランディングへの活用法
3. ブランドコンセプトを決める
ブランドコンセプトとは、ブランドの核となる価値観や方向性のことです。ターゲット層と提供価値を踏まえたうえで決めます。
例としては、ナイキの「体ひとつあれば、誰もがアスリートだ」、スターバックスの「サードプレイス」(自宅でも職場でもない第三の場所)などがあります。ブランドコンセプトは、商品名やロゴ、顧客との接し方など、サービスに関わるものすべてに影響力を持つ重要なものです。
4. ブランド名やロゴを作成する
ブランドコンセプトに沿って、ブランド名やロゴ、キャッチコピーなどを作ります。作成したものからどのようなイメージを受け取るか社内でアンケート調査し、伝えたいものが伝わっているか確認するのも効果的です。商標登録などの法的手続きも忘れずに行いましょう。
5. ブランドのタッチポイントを決める
ブランドのタッチポイントとは、顧客のブランドとの接点のことです。自社のWebサイト、SNS、店舗、カスタマーサービスなどがあります。特にSNSや口コミサイトなどのソーシャルメディアは、以下のグラフのようにブランド認知の向上や顧客とつながるのを目的として、日本のマーケティング担当者の多くが活用しています。
参照:Meltwater「2025年 ソーシャルメディアの最新状況」
ブランドのタッチポイントはターゲット層によって異なります。10代や20代ならTikTok、ビジネス層ならFacebookなど、ターゲット層がよく利用するソーシャルメディアを選びましょう。
▶︎あわせて読みたい:SNSブランディングとは?メリットや成功するためのポイントや事例を解説
6. 社内でブランドの定義を共有する
社内で従業員がそれぞれ異なるブランドの認識を持っていては、顧客に統一されたサービスが提供できず、ブランドイメージが確立されません。ブランディングを成功させるためには、経営者から現場の社員まで社内が一体となって自社のブランドの定義を共有する必要があります。
方法としては、全社員を対象とした説明会で自社のブランド価値を伝えたり、定期的な進捗報告会でブランディングの効果を共有したりするといったものがあります。
7. 効果を測定する
ブランディングの成果を評価するには、ブランドエクイティを定期的に測定することが重要です。ブランドエクイティは、資産としてのブランドの価値のことで、ブランドの認知度やおすすめ度などで測ります。
例えば、アンケート調査やユーザーインタビューを定期的に実施し、ブランド認知率や購入意向率、ブランドロイヤリティの度合いを把握します。調査結果を分析し、課題点があれば改善策を講じましょう。社会環境の変化に伴いブランド価値も変化するため、状況に応じてブランディング戦略の見直しが必要な場合もあります。
ブランディングを成功に導くポイント3つ
ブランディングを成功に導くポイントは以下の通りです。
- ターゲット顧客のニーズを深く理解する
- 自社の独自性を活かしたブランドストーリーを構築する
- 従業員をブランドの体現者として育成する
ターゲット顧客のニーズを深く理解する
ブランディングを成功させるには、ターゲット顧客のニーズを深く理解することが不可欠です。単に自社の商品やサービスの特徴を訴求するだけでは不十分で、顧客がどのような価値を求めているのかを把握する必要があります。
例えば、市場調査やユーザーインタビューを通じて、顧客の潜在的なニーズや課題を明らかにし、それらを解決するためのコンテンツを発信するのも手です。顧客の視点に立ち、共感を得られるブランドメッセージを発信することで、強いブランドロイヤリティを築けるでしょう。
効果的なブランド戦略を立てるためには、ターゲット顧客の理解が欠かせません。
▶︎あわせて読みたい:潜在ニーズとは?見つけ方や重要ポイントを解説
自社の独自性を活かしたブランドストーリーを構築する
ブランディングの成功には、ブランドストーリーの構築が重要です。ブランドストーリーとは、ブランドが誕生したきっかけやこれまでの自社の歩みをストーリー仕立てにまとめたものです。他社にはない特徴や価値が具体的に伝わり、強いブランドイメージを確立できます。
自社の歴史や技術力、社会貢献活動など、差別化できる要素を洗い出し、ブランドの背景にある想いや価値観を伝えることが重要です。単なる商品の羅列ではなく、ストーリーを通じて顧客の共感を得るのです。
また、ブランドストーリーは自社の強みが明確になるという点で、従業員のモチベーションにもつながります。提供する商品やサービスの意義を再認識し、誇りを持ってブランドを体現できるでしょう。
従業員をブランドの体現者として育成する
従業員をブランドの体現者として育成することは、ブランディングの成功に欠かせない要素です。顧客に対して一貫したブランド体験を提供することで、ブランドの価値を維持できるからです。
定期的な社内研修や勉強会を通じて、ブランドの理念や目指す方向性を示すのが方法の一つです。また、社内での働き方にもブランドコンセプトを反映させることで、より従業員にブランドの価値が浸透し、ブランディングの成功に近づけるでしょう。
ブランディングの企業成功事例3つ
ブランディングの成功事例を3つ紹介します。
- 資生堂
- コカ・コーラ
- 兵庫県豊岡市商店街
資生堂:社内外において一貫した美の追求
資生堂は、1872年に日本初の西洋式薬局として創業した、150年以上の歴史を持つ化粧品メーカーです。「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD」を
企業使命とし、化粧品の開発や販売だけでなく、さまざまな社会課題にも取り組んでいます。
例えば、ジェンダーや障がいを超えた平等のために、2030年までに100万人を支援するという明確な目標を打ち出していることが一例です。社内でもLGBTQ+の取り組み、女性や障がい者の登用などを積極的に行っています。
個人の外見のみならず、社会や環境問題においても美というブランドコンセプトを貫いているのが特徴です。社内においてもそのコンセプトが実行されており、従業員の意識を高めることにもつながっているでしょう。
コカ・コーラ:時代に合わせたブランディング
コカ・コーラは、赤いロゴとパッケージデザインで世界中に認知されている飲料ブランドです。コカ・コーラという名前は、Cが2つ並ぶと見た目が印象的になるということから付けられました。
また、ロゴのデザインは時代に合わせてデザインの微調整が重ねられてきたものです。競合であるペプシの人気が高まってきたときはフォントを変え、まったく違った印象になりましたが、顧客からの意見もあり再びフォントのデザインを戻したこともあります。その後は基本のフォントはそのままに、白い波のようなモチーフの位置や形のみを変えるなど、ブランドの根本的なイメージは変えない工夫がされています。
ほかにも、世界的なアーティストやアスリートとのコラボレーションを積極的に行ったり、2030年までに100%サステナブルな素材を使用することを目的に環境への取り組みも強化したりするなど、時代に合わせたブランディングを実践しています。
兵庫県豊岡市商店街:かばんの生産量日本一を活用
兵庫県豊岡市の宵田商店街は、閉店に追い込まれる店が後を絶たず、活気が失われていたことが課題でした。そこで、地域資源であるかばんを活用した「カバンストリート」というコンセプトを立ち上げ、ブランディングを開始します。
かばんの生産地でありながら当初はかばんを扱う店が商店街に1店舗もなかったため、工業組合と商店街を連携させ、少しずつ店舗を増やしていきました。また、かばんの自動販売機やかばんをモチーフとしたベンチなど景観も整備し、かばんのイベントも「カバストマルシェ・プレミアム」と名称を工夫して行いました。
話題性のある仕掛けがメディアに取り上げられたということもあり、商店街には人が訪れ活気が戻りました。2006年に地域団体商標として登録されるまでになり、年間販売個数を数千個から3万個超まで押し上げる成果を生み出しています。地域特有のものを活かしただけでなく、若い世代の意見を施策に取り入れたこともブランディングの成功の鍵でしょう。
参照:中小企業庁「地域資源のかばんを活用した商店街のブランディング」
まとめ|ブランディングで顧客に選ばれる存在になろう
ブランディングは、自社の強みや独自性を活かして、他社との差別化を図るための重要な戦略です。ターゲット顧客のニーズを深く理解し、共感を得られるブランドストーリーを構築することが成功の鍵となります。また、従業員をブランドの体現者として育成し、一貫したブランド体験を提供することも欠かせません。
事例で紹介したような取り組みを参考に、自社のブランディング戦略を立案・実行し、顧客に選ばれるブランドへと成長させましょう。
Meltwaterは、効果的なブランド戦略の策定と実行を支援します。
この記事の監修者:
宮崎桃(Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター)
国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム