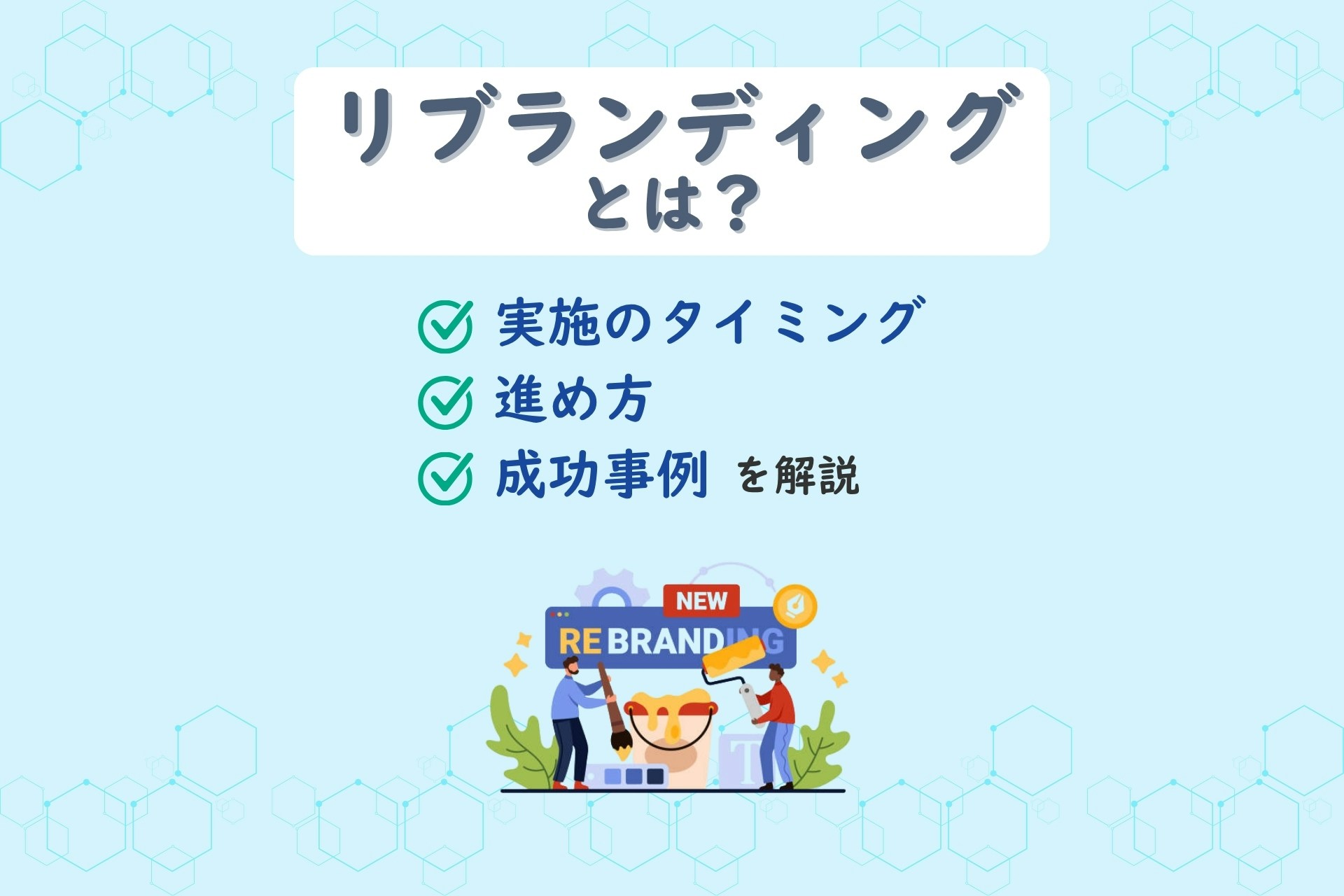時代や顧客ニーズの変化により、既存ブランドが古く感じられたり、売上や認知度が低下したりする課題は多くの企業が直面する問題です。そこでおすすめなのがリブランディングです。
リブランディングとは、既存のブランド資産を活かしながら、時代に合わせてブランドを再構築する取り組みです。本記事では、リブランディングの基本概念に加えて、実施すべきタイミングや失敗しないためのポイント、業界別の成功事例を詳しく解説します。
リブランディングとは?
リブランディングのメリット
リブランディングが必要なタイミング
リブランディングで見直すべきポイント
リブランディングの進め方3STEP
リブランディングで失敗しないためのポイント3つ
【業界別】リブランディングの成功事例
まとめ|顧客ニーズと時代に沿ったリブランディングを
リブランディングとは?
リブランディングとは、再度ブランディングを行うという意味です。ブランディングとは、競合他社との差別化を図り、自社独自の価値を持ったブランドを作ることを指します。
既存ブランドのままでは、時代や顧客ニーズの変化に合わなかったり、他のブランドに埋もれたりしてしまうことがあります。そこで、顧客との関係性を強化し、ブランドの魅力を回復させるために行われるのが、リブランディングです。時代に沿うだけでなく、事業の原点に立ち返る際にも活用されます。
具体的な方法としては、ブランドコンセプトの見直しを通じて、商品のロゴやキャッチコピーの変更、公式SNSでの発信内容の転換、従業員の制服や店舗の内装の改善などがあります。
ブランディングとの違い
ブランディングとリブランディングは、企業や商品、サービスなどのブランドイメージを構築するという点では同じですが、実施するタイミングに違いがあります。
ブランディングは企業設立時や新商品・サービスの開発時に実施されるのに対し、リブランディングは既存のブランドに変化が必要だと判断された時点で実施されます。
リブランディングは、顧客ニーズや市場の変化によって停滞したブランドの競争力を、再び取り戻すための取り組みです。また、経営者が変わったときや事業の節目の年などに行うことで、顧客にブランドの再認識を促す目的もあります。
リニューアルとの違い
リニューアルはリブランディングの一部です。リブランディングは企業の考え方や商品の方向性を見直す取り組みで、リニューアルはリブランディングの手段として、ロゴや店舗の内装などを変えることを指します。リブランディングは企業の変革を指し、リニューアルはそれが形となって表れたものといえるでしょう。
リブランディングのメリット
リブランディングのメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 時代の変化に対応できる
- ブランド資産を活かすことができる
- 新規顧客の獲得が見込める
それぞれ詳しく解説します。
1. 時代の変化に対応できる
リブランディングにより、時代の変化に合わせた価値を提供したり、マーケティング方法を変えたりすることができます。たとえば、グローバル展開を目指す際にロゴに英語表記を加えたり、従来のメールの案内からSNSに切り替えて顧客とやりとりしたりすることです。時代に適応してブランドを変革することにより、現代の顧客に受け入れられる企業イメージを構築できるでしょう。
2. ブランド資産を活かすことができる
リブランディングでは、これまでに蓄積したブランド資産を有効活用できます。長年培ったブランドアイデンティティを土台として、認知度や信頼性、顧客基盤を継承しながら改良を進められます。また、既存のノウハウや設備、販売チャネルなどの経営資源をそのまま活用でき、マーケティングコストが削減できることもメリットです。
▶︎あわせて読みたい:ブランド・エクイティとは?構成要素や測定方法、具体例を解説
3. 新規顧客の獲得が見込める
リブランディングを行えばブランドのイメージが変わるため、これまで自社のブランドに対して興味関心が薄かった顧客層もターゲットになります。ターゲットに効果的にブランド価値を伝えられれば、新たな顧客を獲得することが可能です。
リブランディングが必要なタイミング
リブランディングが必要なタイミングは以下の3つです。
- 経営者が変わったとき
- 事業変革があるとき
- トレンドや時代に合っていないとき
それぞれ詳しく解説します。
経営者が変わったとき
経営者の交代は、従業員も変化に意欲的になる傾向があるため、一丸となってリブランディングを実施する絶好の機会です。新しいリーダーはそれまでの事業を客観的に見ることもできるため、従来とは違った考えやシステムを取り入れやすいということもあります。顧客に対しても変革のメッセージが伝わりやすいタイミングであり、企業の価値を再認識してもらえるでしょう。
事業変革があるとき
事業内容の大幅な変更や新しいビジネスモデルへの転換時も、リブランディングを実施するタイミングとして挙げられます。たとえば、BtoB企業がBtoC市場に参入したり、海外市場へ事業を拡大したりする際には、ターゲット顧客や提供価値が大きく変わります。リブランディングで経営方針を見直すことにより、新しい顧客層へのアプローチが必要です。
トレンドや時代に合っていないとき
ブランドイメージが時代のトレンドから取り残されている場合、顧客離れを招く恐れがあるため、リブランディングによる軌道修正が必要です。
たとえば、近年では環境意識の高まりによりサステナブルな事業展開に価値が置かれる傾向があります。働き方においても、コロナ禍を経てリモートワークや副業が可能など多様化が進んでいます。このような現代の価値観から大幅にずれると、企業イメージの低下につながりかねません。採用活動にも影響するでしょう。
▶︎あわせて読みたい:コーポレートブランディングとは?目的や進め方、成功事例を解説
リブランディングで見直すべきポイント
リブランディングを実施する際は、以下の点を見直しましょう。
- ビジュアルイメージ
- 商品・サービスの内容
- ブランドのメッセージ・発信内容
それぞれ詳しく解説します。
ビジュアルイメージ
ビジュアルイメージの刷新は、リブランディングにおける代表的な手段です。具体的には、ロゴデザインやフォント、パッケージデザイン、ユニフォーム、オフィスの内装などが対象となります。重要なのは、ターゲット顧客や伝えたいブランドイメージに合わせることです。従来の堅いイメージから親しみやすさを演出したい場合、角張ったロゴを丸みのあるデザインに変更する方法などが挙げられるでしょう。
商品・サービスの内容
リブランディングでは、商品やサービスの内容そのものを見直すことも重要です。たとえば、健康志向の高まりに合わせて、食品の素材やカロリーを調整したり、環境意識の向上に応じて製造方法を持続可能なものに変更したりします。デジタル化の進展により、従来の店舗販売にオンラインサービスを追加するのも良いでしょう。
ブランドのメッセージ・発信内容
リブランディングでは、企業が外部に発信するメッセージの見直しが重要になります。具体的には、キャッチフレーズやスローガン、広告の文言、会社案内の内容などです。ブランドガイドラインを整備し、すべての発信内容を統一することで、顧客に対して新しいブランドイメージを分かりやすく伝えられるでしょう。
▶︎あわせて読みたい:ブランドマネジメントとは?メリットや効果的なステップ・成功事例を解説
リブランディングの進め方3STEP
リブランディングは以下の手順で実施しましょう。
- 現状分析・市場調査
- 戦略立案
- 新ブランドの周知・浸透
順番に解説します。
1. 現状分析・市場調査
リブランディングを実施する際は、まず現在のブランドに関する詳細な分析と調査が必要です。売上の推移や競合他社の分析、市場トレンドなど客観的なデータを収集します。
特に重要なのは、企業が伝えたいブランドイメージと顧客が実際に感じているイメージの間にギャップがないかを確認することです。この段階で明確な課題が見つからない場合は、リブランディング自体を見直すことも重要でしょう。
▶︎あわせて読みたい:市場調査とは?メリットや調査方法、実施の流れを解説
2. 戦略立案
現状把握と分析を行い、リブランディングの実施が決まったら、どのようにブランドを再構築するか検討しましょう。まずは、自社が理想とするブランドイメージを明確にします。次に、消費者アンケートを参考にしながら、消費者がもつイメージとのギャップを埋めるための方法を検討します。具体的な方法は以下のように様々です。
- 社名の変更
- ロゴの変更
- キャッチコピーの変更
- 自社サイトのリニューアル
- パンフレットの刷新
- 社内の働き方改革
どの方法を選択するかは、状況によって異なります。たとえば自社に対する信用が著しく低下している場合は、社名を変更するのも効果的です。既存のものを活かしながら新しい企業の形をアピールするには、ロゴやキャッチコピーなどの変更が良いでしょう。
3. 新ブランドの周知・浸透
戦略を実行に移して新しいブランドを周知し、浸透させます。社内の理解と協力を得てから、外部へのアプローチを開始することで、一貫したメッセージを発信できます。
社内への周知
従業員一人ひとりがブランドの体現者となるため、社内への周知は最も重要なプロセスです。社内広報誌や説明会などを通じて、リブランディングの目的や変更点、今後の方向性を詳しく伝えましょう。従業員からの質問にも応じ、新しくなったブランドへの解釈を社内でできるかぎり統一します。
社外への周知
社外への周知は、公式のWebサイトやSNSでの発信のほか、メディアを通じたプレスリリースの配信も信頼性があり、広範囲への周知が可能になります。
プレスリリースを利用する際には、ターゲットに応じて最適なメディアを選択することが重要です。Meltwaterのメディアリレーションツールを活用することで、効率的にメディア対応と配信効果の測定ができます。
リブランディングで失敗しないためのポイント3つ
リブランディングで失敗しないためのポイントは以下の3つです。
- 既存ブランドの良さを活かす
- ユーザー目線で考える
- 継続して取り組む
それぞれ詳しく解説します。
1. 既存ブランドの良さを活かす
リブランディングを実施する際は、既存ブランドの良さを見直したうえで、変える要素を明確化しましょう。長年存在しているブランドには、信頼が生まれます。リブランディングでブランドイメージがあまりに大きく変化してしまうと、同じブランドであることがわからなくなってしまい、既存顧客を逃しかねません。
ロゴやサイトのデザインは変えても、イメージカラーは変えないようにするなど、これまでに積み上げてきた世界観を大切にして、一貫性を持たせながらリブランディングを実施すれば、既存顧客も変化を受け入れてくれるでしょう。そして、新たな顧客の獲得にもつながるはずです。
2. ユーザー目線で考える
リブランディングでは、企業目線ではなくユーザー目線で戦略を立てることが重要です。企業が良いと思うものを提供しても、顧客が求める価値やニーズに合っていなければ、的外れなブランド変更になってしまう可能性があります。
顧客の声を収集する方法として、アンケート調査やインタビューに加え、SNS上の口コミや評判を分析することが効果的です。顧客ニーズは、顧客自身がわかっていないこともあります。Meltwaterのソーシャルリスニングツールを使えば、リアルタイムで顧客の声や感情を把握・分析でき、潜在ニーズを探ることも可能です。実際の顧客ニーズに基づいてブランド戦略を検討することで、リブランディング後の顧客離れを防げます。
<Meltwaterのソーシャルリスニング(クチコミ分析)ツール>
3. 継続して取り組む
リブランディングで成果を出すには、短期的な結果に左右されてはいけません。成果が出るまでには時間を要するものです。PDCAサイクル(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)を回しながら、継続して取り組む必要があります。
定期的に消費者アンケートを実施したり、売上を計測したりしながら、ブラッシュアップを図りましょう。
【業界別】リブランディングの成功事例
リブランディングの成功事例を業界別に5つ紹介します。
化粧品業界:よーじや
よーじやは、化粧品や雑貨販売をメインとする京都の会社です。明治時代の創業当初に、地元の人から呼ばれていた愛称が社名になっています。
しかし1990年代のあぶらとり紙ブームにより「京都みやげのあぶらとり紙屋さん」というイメージが定着してしまっていたのです。2024年に創業120年を迎えたことを機に、「おみやげの店」から「おなじみの店」へと原点に戻るため、観光客だけでなく地域の顧客にも愛されるブランドの再構築を目指すことにしました。
実行した施策は、コーポレートキャラクターとロゴマークを60年ぶりに刷新するという大胆なものでした。ポイントは元のデザインを活かした点です。1965年から使用していた手鏡に映る女性のデザインをもとに、やさしい色づかいで丸みのあるキャラクターに仕上げました。「みんなが喜ぶ京都にする」というコーポレートスローガンにも合った温かみのあるイメージです。従来のデザインも商品に引き続き使われており、新しいものと古いものが調和した施策となっています。
アパレル業界:ユニクロ
ユニクロは低価格をアピールしヒット商品を生み出してきましたが、2000年代初頭には安っぽいイメージができてしまったことが課題でした。世界進出を視野に入れた同社は、「Made in Japan」の強みをアピールするためリブランディングすることを決定しました。
クリエイティブディレクションに佐藤可士和氏を起用し、英文字とカタカナそれぞれをシンプルなロゴに刷新。低価格というコンセプトは維持しながら、エアリズムやヒートテックなど高品質・高機能商品を展開することで、「低価格」から「おしゃれで機能的な定番ブランド」としての地位を確立しました。
食品業界:湖池屋
株式会社湖池屋は、スナック菓子や食品を製造・販売するメーカーです。2016年に新社長の就任をきっかけに、ポテトチップスのリブランディングに着手しました。スナック菓子が低価格競争に陥っている中で原点に返り、おいしいポテトチップス作りに妥協しないプライドを「KOIKEYA PRIDE POTATO」として表現し、2017年に販売しました。
新しいパッケージのデザインが多くの顧客に受け入れられ、発売から1か月弱で品切れになるなど大きな話題を集めました。しかし、2018年と2019年は、発売当初ほど売上が伸びませんでした。
そこで再びリブランディングを実行します。前回の反省点は、デザインを一新したことで、親しみやすさや湖池屋というブランドが見えづらくなってしまったことです。それを踏まえ、「湖池屋プライドポテト」というカタカナ表記にし、パッケージも2017年のものに立ち返って白を背景としたデザインにしました。結果、2020年2月には2017年2月時点よりも売上が1.2倍伸びました。
産業機械業界:ヤンマー
ヤンマーホールディングス株式会社は、エンジンなどを開発・販売する老舗のメーカーです。大地(農業)、都市(エネルギー・建設機械)、海(マリンインダストリー)の分野で事業展開をしていましたが、日本では農業用機械メーカーとして知られているのに対し、欧米では船舶用のエンジンメーカーとして認知されていました。
環境問題や食の安全への関心の高まりという時代の変化を受け、社会問題に対応できる企業としてのブランドイメージを確立するために、2013年に立ち上げたのが「ヤンマープレミアムブランドプロジェクト」です。ロゴや農作業着、トラクターなどのデザインを刷新したほか、分野を超えてブランドイメージを統一し、100年培ってきたヤンマーの技術力の高さをアピールしました。
まとめ|顧客ニーズと時代に沿ったリブランディングを
リブランディングのメリットや実施すべき効果的なタイミング、企業の成功事例などを解説しました。変化の激しい現代社会では、一度築き上げたブランドも、必要に応じて刷新していく必要があります。リブランディングを実施すれば、既存の顧客を維持しつつ、新たな顧客を獲得することも可能です。
Meltwaterではリブランディングに役立つツールを提供しています。ツールを利用すれば、ブランド価値の可視化や数値データに裏付けされた戦略立案が可能になります。リブランディングの実施の際には、ぜひご活用ください。
この記事の監修者:
宮崎桃(Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター)
国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム