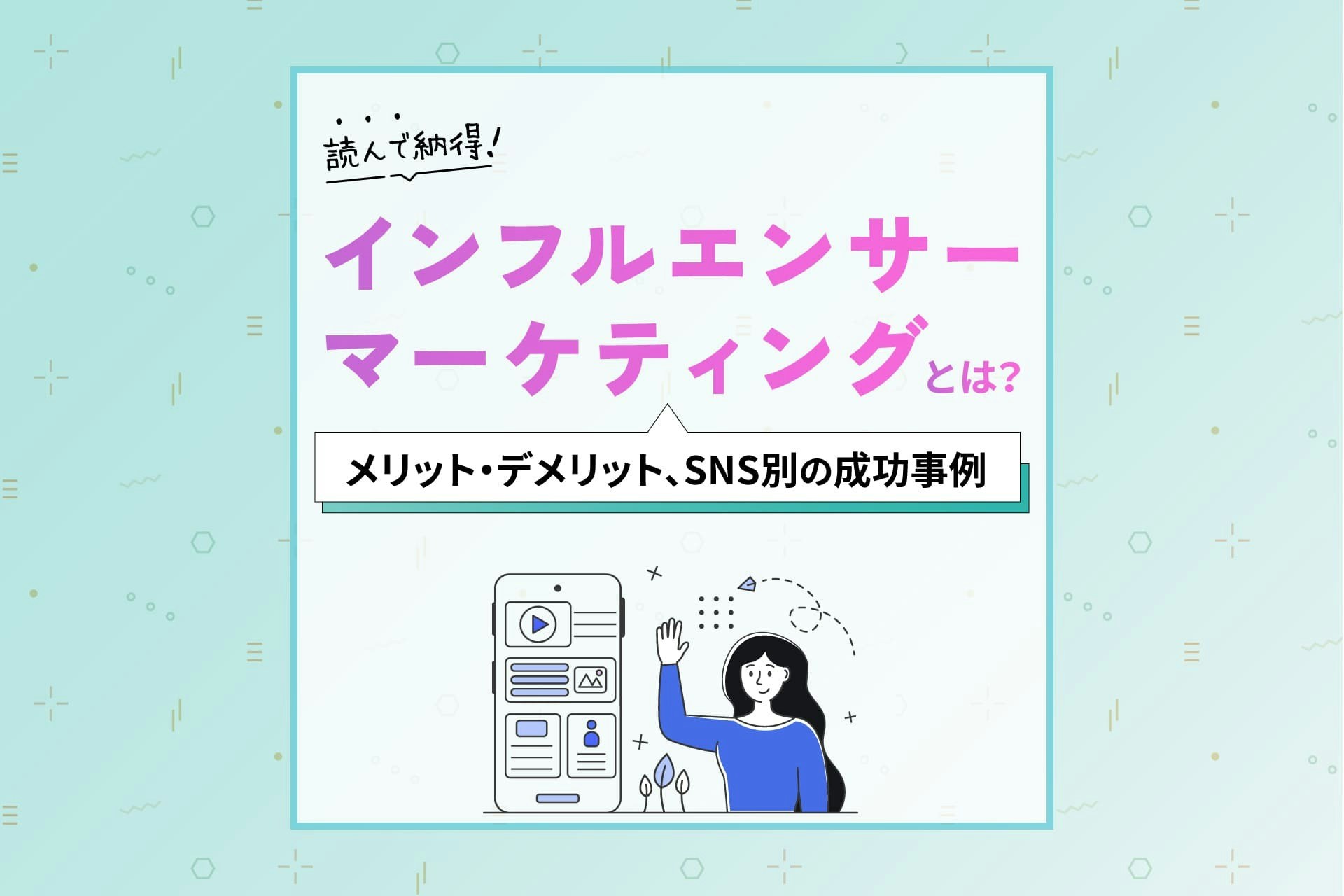商品の認知や売上アップに宣伝は欠かせませんが、その中でも「インフルエンサー」を起用する方法が増えています。
SNSの普及により、フォロワー数を多く抱える人がマーケティングにおいても影響力を持つようになりました。
本記事では、事業者に向けてインフルエンサーマーケティングの基本知識をわかりやすく解説します。
メリット・デメリットや具体的な依頼方法まで幅広く紹介します。
インフルエンサーマーケティングとは?
インフルエンサーマーケティングのメリット
インフルエンサーマーケティングのデメリット
インフルエンサーマーケティングで活用する主要SNS
インフルエンサーの種類
インフルエンサーマーケティングの具体的な流れ
インフルエンサーへの依頼方法
インフルエンサーマーケティングを成功に導くポイント
【SNS別】インフルエンサーマーケティングの成功事例
まとめ|需要の高まるマーケティング手法
インフルエンサーマーケティングとは?
インフルエンサーマーケティングとは、インフルエンサーを起用したマーケティング手法のことです。
インフルエンサーとは、市場トレンドや消費者の思考・行動に大きな影響を与える人のことで、特にSNSで注目を集めている人を指します。勢力・影響・効果を表す単語である「influence」が語源です。
普段SNSで馴染みのあるインフルエンサーが商品アピールをするため、広告として押し出している感じがなく、フォロワーの共感を集めやすい手法として注目を集めました。
ROI(投資に対する利益率)を高めるのにも、インフルエンサーマーケティングは有効であることがわかっています(参考:Whalar 2019年の調査)。
上のグラフは、国内のインフルエンサーマーケティングの市場規模を表しています。
年々増加傾向にあり、2027年には2023年比1.8倍(1,302億円)に到達するだろうと予想されています。
インフルエンサーマーケティングのメリット
ここからは、インフルエンサーマーケティングのメリットを解説します。なぜ大手企業から中小企業までさまざまなインフルエンサーマーケティングが活用されているのか、その理由を深堀りしていきましょう。
1. 広告感がなくユーザーに受け入れられやすい
Meltwaterが2025年2月に更新した2025年グローバルデジタルレポートによると、ソーシャルメディアを利用する主な理由として、インターネットユーザーの23.4%が「毎週インフルエンサーの動画を視聴する」、19.7%が「インフルエンサーや有名人をフォローする」と回答しています。
インフルエンサーマーケティングは、インフルエンサー本人が商品・サービスをおすすめする形で配信されることが多く、広告感があまりありません。「自分が好きな人が発信している内容だから見てみたい」と自然に思わせるため、最後までプロモーションを見てもらえる可能性が高まります。
2. 情報の拡散が期待できる
インフルエンサーマーケティングの内容に共感してもらうことができれば、SNS上の「いいね」や「リポスト(リツイート)」などによる拡散が期待できます。情報が拡散されればインフルエンサーのフォロワー以外にも情報を届けることができ、「注目されているコンテンツ」としてさらに人々の関心を引くことができるでしょう。
関連記事「口コミマーケティング」に関する詳しい記事はこちら
口コミマーケティングとは?メリットや代表的な手法・成功事例を解説
3. ユーザーの行動を分析しやすい
インフルエンサーマーケティングはインターネットで行われるのが一般的であり、ユーザー行動を分析できるのがメリットです。例えば、インフルエンサー経由でサイトに訪れたユーザーが、どの場面で会員登録や商品購入などのコンバージョンしているか(または離脱してるか)を調べれば、ページの改善に役立ちます。
4. ジャンルに合わせたターゲティングがしやすい
商品・サービスのジャンルに合ったインフルエンサーをキャスティングできれば、ターゲティングも容易です。例えば、キャンプに関心がある人をターゲットにしたい場合は、普段キャンプ関連の情報を発信しているインフルエンサーを起用すれば、キャンプに関心があるフォロワーが自然とついてきます。インフルエンサーを選ぶだけで、ターゲティングの手間を省けます。
5. SEOの強化につながる
SEOとは、検索エンジンで自社サイトを上位に表示させるための施策索のことです。SEO対策すると、サイトの検索数が増えます。
インフルエンサーマーケティングに成功すると、ランディングページ(インターネット広告をクリックした先のページ)や自社ECサイトへのアクセス数が伸び、SEOの強化にもつながります。
インフルエンサーマーケティングのデメリット
一方で、インフルエンサーマーケティングにはデメリットもあるので注意しましょう。代表的なデメリットを解説します。
1. ステルスマーケティングだと思われやすい
ステルスマーケティング(通称:ステマ)とは、広告やプロモーションであるにもかかわらず、そのことを提示しない違法行為です。
あくまでも一般消費者であるかのように宣伝することは景品表示法における違法行為であると、2023年3月に消費者庁が公表しました。(2023年10月から規制開始)
インフルエンサーに依頼して宣伝を行う場合は「広告」「PR」などを表示し、あくまでも宣伝案件であることがわかりやすいようにする対策が求められます。しかし、普段から口コミ風の投稿が多く、案件であってもステルスマーケティングだと思われやすいのがデメリットです。
2. 炎上リスクがある
事前に内容をチェックしたうえでインフルエンサーに投稿してもらっても、内容次第では炎上することが少なくありません。特定のユーザー層に配慮のない投稿であったり、意図せず差別的な表現が使われてしまっていたりすると、ユーザーの不信感を招いてしまいます。
自社のプロモーションに関係のない投稿であっても、炎上は起こり得ます。インフルエンサーのイメージが自社イメージに直結することを意識して、キャスティングをするのが大切です。
3. キャスティングに時間がかかる
インフルエンサーの数は多く、自社に最適なインフルエンサーをキャスティングするまでに時間がかかります。
また、インフルエンサーがオファーを受けてくれるとも限りません。1名のインフルエンサーをキャスティングするだけでも、通常10〜20人程度にオファーを出す必要があります。十分な工数を用意し、ギリギリのスケジュールにならないよう配慮しておきましょう。
4. インフルエンサーによっては費用対効果が見合わない
キャスティングするインフルエンサーによっては、費用対効果が見合わないこともあります。例えば、商品紹介の質が低く魅力がうまく伝わらないと、想定していたような効果は得られません。他にも、広告感が出ないよう本音で口コミを話したら、デメリットばかり目立ってしまったというケースも考えられます。
5. 投稿内容を細かく指定できない
インフルエンサーマーケティングの場合、投稿する文面や動画の編集方法は、ある程度インフルエンサーに任せることが前提となります。「この部分を強調して発言してほしい」などのオーダーはできますが、自社で作成したコンテンツをそのままアカウントだけ借りて投稿してもらうことはできないのが一般的です。
多くのファンが求めているのはそのインフルエンサーにしかない雰囲気であり、自社で投稿を作成すると「その人らしさ」が失われてしまいます。単なる名前貸しでの投稿にならないよう、ある程度の裁量を与えながら打ち合わせしていくことが大切です。
インフルエンサーの種類
インフルエンサーの種類は、フォロワーの数によって分けられています。一般的にフォロワーが多い方がより影響力が高いとされており、その分予算もかかります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| インフルエンサーの種類 | フォロワー数 | 特徴 |
|---|---|---|
| メガインフルエンサー | 100万人以上 | 活動拠点のSNSが多岐に渡り、テレビやラジオにも出演することが多いため、フォロワー以外にも絶大な知名度を誇る |
| ミドルインフルエンサー (マクロインフルエンサー) | 10万人~100万人規模 | テレビなどメディアへの露出はまだ少ないものの、専門性の高いジャンルでコアなファンを獲得していることが多い |
| マイクロインフルエンサー | 1万人~10万人規模 | ファン同士の交流が盛んなインフルエンサーでもあるため、口コミによるコアなファンの獲得を目指したいときにも向いている |
| ナノインフルエンサー | 1000人~1万人規模 | ニッチな層(他がねらわないような小規模な層)をファンに抱えていることが多い |
▶︎あわせて読みたい:
インフルエンサーマーケティングで活用する主要SNS
インフルエンサーマーケティングで活用されることの多いSNSは、それぞれのプラットフォームごとに主要ユーザー層や活用法が異なります。特徴をつかんで活用しましょう。
| SNS | 特徴 |
|---|---|
| YouTube | ・長編動画で訴求できる ・メイク動画や使い方説明などHow to系と相性が良い ・10代から60代以上まで幅広く使われている |
| ・若年層と女性ユーザーが多い ・美容系やファッション系と相性が良い ・写真映えする商品のアピールに最適 | |
| ・文章量の多いコンテンツでも投稿できる ・リポスト機能による拡散力が高い ・珍しいコンテンツやくすっと笑える投稿に最適 | |
| TikTok | ・10代から20代のユーザーが多い ・レコメンド機能が強く潜在層へのアプローチに最適 ・ダンスや音楽との組み合わせに強い |
インフルエンサーマーケティングにおけるチャネルとして最も効果的だと思うもの2つを、アジア太平洋地域にある各社約400名の担当者に聞きました。結果、1位はInstagram(51%)、2位はTikTok(31%)、3位はFacebook(約25%)でした。
出典:2024年ソーシャルメディアの最新状況(Meltwater)
インフルエンサーマーケティングの代表的な手法
ここでは、インフルエンサーマーケティングで使われる代表的な手法を解説します。目的に合わせて使い分けられるよう、まずはそれぞれの概要をチェックしてみましょう。
ギフティング
ギフティングは、インフルエンサーに実際の商品を渡して(もしくはサービスを体験してもらって)感想を投稿してもらう手法ですいます。商品・サービスの紹介をする際に最もよく活用されます。
現地訪問
アプローチしたい商材がイベント・観光スポット・テーマパークなどの場合、インフルエンサーに現地に行ってもらう「現地訪問」も方法のひとつです。現場の様子をSNSや動画で投稿してもらうことで、「自分も行ってみたい」「楽しそう」というユーザーのわくわく感を引き出せます。
コラボレーション
コラボレーションとは、自社とインフルエンサーが共同で商品開発やイベントの企画をする方法です。注目を集めやすい分、企画段階からインフルエンサーに関わってもらう必要があり、膨大な時間を要します。
ライブ配信
SNSプラットフォームのライブ配信機能を活用し、商品を紹介してもらう手法です。リアルタイムでの配信であるため作りこまれている感がなく、実体験を届けられます。フォロワーの属性に合った曜日・時間帯に配信する必要があります。
インフルエンサーマーケティングの具体的な流れ
次に、インフルエンサーマーケティングをする具体的な流れを紹介します。準備段階で必要な項目を可視化し、無理のないスケジュールに落とし込むためにも、下記を参考にしてみましょう。
1. 目的や予算などの設定施策
まずはインフルエンサーマーケティング施策のプランニングを実施します。
以下のような項目を設定します。
- 目的の設定(例)
ブランドの認知向上
ブランドイメージの向上
フォロワー数を増やす
売上アップ - KPI(目標を達成するための指標)の設定 (例)
達成までの期間も決めておくと良いです。
自社サイトへの訪問ユーザー数
コンバージョン率、
インプレッション(広告やコンテンツの表示数)
リポスト(リツイート)数やいいね数
コメントでのポジティブな反応率 - ターゲットの設定(例)
年齢層
年収
居住地
休みの日の過ごし方
よく使うSNS - 予算の設定
インフルエンサーのフォロワー数が多いほど、依頼のコストもかかります。
目安は「フォロワー数 × 2~4円」です。Instagramを例にすると、5000 人~1万人のフォロワーを持つナノインフルエンサーの場合、1案件の依頼コストは平均9,605円となっています(参考:LIDDELL 2016年の調査)。
この他、必要に応じて、ギフティングの送料、現地訪問の交通費、キャスティング専門会社の仲介手数料、インフルエンサーマーケティングツールの利用料などがかかります。
2024年にインフルエンサーマーケティングにかける予算を、「前年より増やす」「前年と同じ」と答えた企業は、アジア太平洋地域で52.5%でした(参考:Meltwater 2025年の調査)。インフルエンサーマーケティングの重要性を理解したうえで、予算を多めに考えると良いでしょう。
2. キャスティング
方向性が決まったら、インフルエンサーのキャスティングに移ります。インフルエンサーの採用数は1~10名の企業が多いです(参考:Meltwater 2025年の調査)。以下を基準にインフルエンサーの特徴をつかみ、目的やターゲット像と照らし合わせましょう。
キャスティングのポイント
- フォロワーの人数とそのSNS媒体や
- 投稿頻度
- フォロワーの特徴(ターゲット像と合っているか) など
インフルンサーごとの特徴も併せて整理しておくのがおすすめです。
インフルエンサーの数は膨大なため、ツールを使用して最適なインフルエンサーを見つけ出すのがおすすめです。
また、依頼の際は、禁止事項や緊急連絡先も明記した契約書を作成するなどして、透明性を維持していくことも大切です。
また2025年にMeltwaterがSNSマーケターを対象に行った調査では、自社でソーシャルリスニングを実施する目的として「インフルエンサーやオピニオンリーダーの特定」を挙げた回答者が30%以上となりました。
ソーシャルリスニングもインフルエンサーのキャスティングに有用な手法と言えるでしょう。
3. 施策を実施
インフルエンサーと投稿内容をすり合わせたら、施策を実施します。
投稿状況の確認も同時並行で進めていきましょう。
4. 効果検証
投稿の完了後、効果を検証します。
最初に策定したKPI(目標を達成するための指標)を達成できているかチェックします。次のインフルエンサーマーケティングに向けて改善すべきポイントがあれば、早い段階で記録に残します。
インフルエンサーへの依頼方法
インフルエンサーへ依頼する方法として、主に下記の3つが挙げられます。コストや工数のバランスを見ながら、自社にとって最も良い方法を探りましょう。
自社で直接コンタクト
自社で直接コンタクトを取る場合、インフルエンサーのアカウントにダイレクトメールを送信して接点を作るところから始めます。プロジェクトの概要などを簡潔にまとめながら、興味を持ってもらえるような文面を作成しましょう。
キャスティング専門会社に依頼
キャスティング専門会社に依頼し、自社商材に合ったインフルエンサーを紹介してもらう方法もあります。プロのマーケターがサポートしてくれるので、仲介手数料がかかりますが、ノウハウのない企業でも取り組みやすくなります。効果測定などの具体的な手法も教えてもらえれば、自社にナレッジを蓄積するきっかけになるかもしれません。
インフルエンサーツールを活用
インフルエンサーツールを使えば、PDCA(計画→実行→評価→対策)サイクルを素早く回せます。例えば、以下のようなことが可能です。
- 条件に合致するインフルエンサーのリストアップ
- 各インフルエンサーの影響力をスコアで算出
- フォロワーの特徴の把握(年齢層・好きな有名人・訪問サイトなど)
- プロジェクトのスケジュールやマーケティング予算の一元管理
- 投稿への反応率やハッシュタグ分析
失敗しない!インフルエンサーマーケティングツールの選び方
⇒解説資料のダウンロードはこちらから
インフルエンサーマーケティングを成功に導くポイント
インフルエンサーマーケティングを成功に導くポイントを解説します。参考になる項目があれば、自社の施策にも生かしていきましょう。
1. 自社の価値観に合ったインフルエンサーを見つける
ユーザーに商品・サービスの魅力を伝えるには、それを引き立たせてくれるインフルエンサーを選ぶことが必要です。一度信頼を得たブランドは、その後多少のミスがあったとしても、67%のユーザーはブランドに対する信頼が揺るがないという調査結果があります(参考:Meltwater 2023年の資料)。長期的な影響力を考慮すると、インフルエンサー選びはかなり重要です。
インフルエンサーは幅広くいるため、ツールを利用してある程度絞り込むこという方法もあります。しかし、どのくらい価値観に合っているかは繊細なものであり、一人ひとりを吟味することが必然となるでしょう。手間とコストがかかりますが、影響力とのバランスを考えると良いです。
2. マイクロインフルエンサーやナノインフルエンサーと協力する
インフルエンサーは、フォロワー数によって4種類に分かれますが、その中でもマーケティングの活用におすすめなのがマイクロインフルエンサーとナノインフルエンサーです。フォロワー数は少ないものの、その分フォロワーと親密な関係が築かれていることが多く、コアなファンに影響力があります。
マイクロインフルエンサーによる投稿のエンゲージメント率は2021年に91%にもなり、2023年にナノインフルエンサーを起用すると答えた企業は39%でした。コストパフォーマンスを狙うなら、マイクロインフルエンサーやナノインフルエンサーの活用を考えてみましょう。
出典:2023年ソーシャルメディアの最新状況(Meltwater)
3. ソーシャルコマースを活用する
ソーシャルコマースとは、SNS(ソーシャルメディア)とEC(イーコマース)を融合し商品販売を行うことです。
SNSで宣伝しECサイトに誘導するという方法もありますが、ソーシャルコマースは商品の認知から購入まで、SNS上で完結することができます。インフルエンサーからのおすすめ情報を見たりユーザー間で交流したりしながら、ECサイトへ移動することなくショッピングを楽しめます。
ソーシャルコマースを利用した人は利用していない人に比べ、同じショップやインフルエンサーから再度購入する率は1.4倍です(参考:Meltwater 2023年の資料)。インフルエンサーだけでなく、ソーシャルコマースも活用することで、効果アップが期待できます。
【SNS別】インフルエンサーマーケティングの成功事例
インフルエンサーマーケティングの成功事例を、プラットフォームごとに紹介します。
1. YouTubeの事例|UNIQLO×なぐもふうか
アパレルブランド「UNIQLO」は、YouTuberなぐもふうか.さんを起用したプロモーションを行いました。着用イメージやサイズ感などHPだけでは伝わりづらい情報を中心に動画で解説しており、新作商品の特徴がわかりやすいと評判になりました。
着回しや小物を使ったコーディネートなども参考になります。
2. TikTokの事例|KKday×NEOトラベラーズ
KKdayは航空券から旅行ツアーまで扱っている予約専門サイトです。関西を中心に見どころスポットを発信しているNEOトラベラーズさんを起用し、お得な大阪周遊パスをアピールしました。
NEOトラベラーズさんは、普段からコストパフォーマンスに優れた旅行の楽しみ方を紹介しています。プロモーション内容とインフルエンサーのイメージがぴったりなのが特徴です。
3. Instagramの事例|MIRIMU(ミリム)×おっしー
コスメブランドMIRIMU(ミリム)は、化粧品など美容関連の商品サービスをレビューしているインフルエンサー、おっしーさんとタイアップしました。実際の使用感が写真と動画で紹介されています。リップやアイシャドウのカラー比較も載せており、一人ひとりのパーソナルカラーを引き出したいMIRIMU(ミリム)の訴求ポイントが、うまく取り入れられています。
4. Twitterの事例|エバラ×料理研究家リュウジ
参照:リュウジさん X(Twitter)
焼肉のタレで有名な「エバラ食品」は、料理研究家として数々のバズレシピを生み出してきたリュウジさんをキャスティングしています。焼肉のタレを使った簡単・手軽・安価な時短レシピを複数配信したことで、主婦層や一人暮らし家庭から支持されました。
共働きで忙しい子育て家庭にも支持されており、YouTubeで動画レシピも提供しています。
まとめ|需要の高まるマーケティング手法
インフルエンサーマーケティングは、広告感なく商品サービスの魅力を伝えたいときに有効です。日頃から親近感を抱いているインフルエンサーが商品のアピールをしていれば共感が沸き、気になって購入するユーザーも多くなるでしょう。より高い効果を狙いたいときは、インフルエンサーのキャスティングから使用SNSの選定まで、入念な計画を作る必要があります。
Meltwaterは、インフルエンサーマーケティングに役立つツールを提供しています。インフルエンサーのキャスティングやその後の効果検証に役立つAI搭載ツールをお探しの方は、ぜひお役立てください。
インフルエンサーマーケティングの課題はMeltwaterへご相談。
ブランドに最適なパートナーの発掘と長期的な関係構築、業務の効率化をサポートします。
⇒Meltwaterへお問い合わせ
この記事の監修者:
馬見塚 堅 (Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター)
2016年にMeltwater Japan株式会社入社。
外部データ活用に向けてマーケティング・企画・広報部向けのコンサルティングを7年で200社以上を担当。 現在は、大手企業や官公庁向けのソリューション企画に従事。インフルエンサーマーケティングや消費者インサイトに関するセミナー実績多数。
趣味:旅行、子育て情報収集、仮想通貨、サッカー観戦(川崎フロンターレの大ファンです)