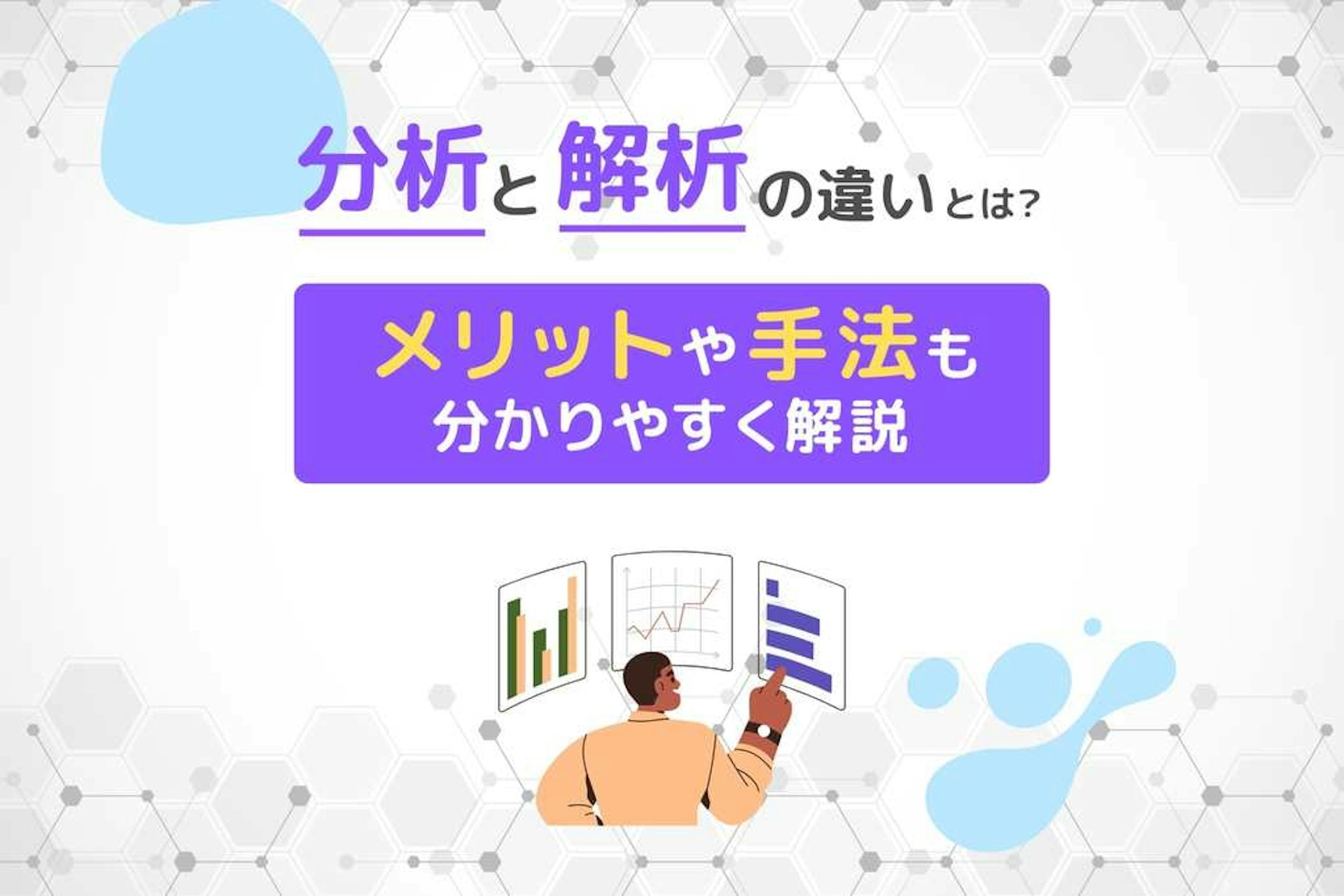データの「分析」と「解析」は、同じようで明確な違いがあります。分析と解析のどちらも行うことで、マーケティング施策に活かすことができます。
この記事では、分析と解析の定義や違いを整理した上で、主な手法、導入によるメリットや注意点、企業の成功事例についても紹介します。
データ分析とデータ解析の違いとは?
分析と解析のそれぞれの目的
データ分析・解析を行うメリット3つ
データ分析・解析の主な手法
データ分析・解析を行う際の注意点3つ
データ分析・解析のツールを活用した企業の成功事例
まとめ|分析と解析の違いを理解し戦略に差をつけよう
データ分析とデータ解析の違いとは?
データ分析は、対象を細かい要素に分けて構造や傾向を把握するプロセスです。対してデータ解析は、その分析結果をもとに理論的に因果関係を導き出す作業を指します。
例えば店舗でチラシ配布を行った際に、来店者の年代や性別などの属性を整理・分類するのが「分析」にあたり、若年層の来店が多かった背景や要因を探るのが「解析」となります。
言い換えれば、分析は「分けて整理すること」、解析は「原因や意味を深掘りすること」と捉えると、それぞれの違いがより明確になるでしょう。なお、実務ではこれらは連続して用いられることが多く、厳密な使い分けが求められないケースもあります。
分析と解析のそれぞれの目的
集めたデータを業務に活かすためには、まず「分析」と「解析」の目的や役割の違いを正しく理解することが重要です。ここでは、それぞれが担う役割や特徴を整理し、具体的な活用シーンを交えてわかりやすく紹介します。
データ分析の目的
データ分析の主な目的は、現状を客観的に把握することです。
例えばWebサイトの直帰率やページビュー、顧客の購入履歴などの数字をもとに、どのような傾向があるのかを明らかにしていきます。数値を表やグラフに可視化するなど、全体像を見える化することが重要です。何が起きているかを把握することで、改善すべき箇所や注目すべきポイントが見えてきます。
あくまで「事実を整理する」ことが分析の役割であり、原因の特定や仮説の検証は含まれません。次のステップである解析の基盤となる工程といえるでしょう。
データ解析の目的
データ解析の目的は、背景や要因を解明することにあります。
Webサイトの直帰率が高いという結果が出た場合、どの要素が原因かを探るのが解析の役割です。広告との内容のズレ、導線の不備、読み込み速度の問題など、複数の可能性を考えながら仮説を立てて検証していきます。
このように、解析は意思決定や改善策の立案に数字の変化に理由を見出すことで、次に取るべき施策の方向性が明らかになり、実務において重要な役割を果たします。
データ分析・解析を行うメリット3つ
データの分析・解析には、多くのメリットがあります。ここでは、ビジネスを前に進めるうえで特に重要といえる3つのメリットについて具体的に紹介します。
データドリブン経営につながる
データドリブン経営とは、蓄積された情報に基づいて意思決定を行う経営手法のことです。個人の主観や過去の経験に偏らず、客観的な判断が可能になります。社員も意思決定の根拠に納得できるため、一丸となって目標に向かうことができ、組織運営が効率的になることもメリットです。
過去の成功事例や失敗要因もデータとして蓄積され、将来の変化を予測することも可能なため、PDCAサイクル(Plan=計画、Do=実行、Check=評価、Act=改善)の質の向上も見込めるでしょう。
▶︎あわせて読みたい:データドリブン経営とは?取り組むメリットや進め方、成功事例を解説
迅速な意思決定ができる
意思決定のスピードは、競争の激しいビジネス環境において大きなアドバンテージとなる要素です。ツールを使ってデータを分析・解析することで、状況に応じた判断材料をすばやく入手でき、議論の時間を削減できます。
▶︎あわせて読みたい:データドリブンPR ~KKD(経験・勘・度胸)に頼らないPR戦略〜
潜在的な顧客ニーズが発見できる
データを整理して原因を知ることで、顧客自身も意識していない関心や不満が浮かび上がってくることがあります。ニーズに先回りした商品開発やサービス改善が可能になり、既存顧客の満足度向上にも寄与するでしょう。
▶︎あわせて読みたい:潜在ニーズとは?見つけ方や重要ポイントを解説
データ分析・解析の主な手法
自社が抱える課題や目指す成果に応じて、最適な分析手法を選定することが重要です。ここでは代表的な手法を紹介し、それぞれの特長と使いどころを解説します。
RFM分析
RFM分析は、顧客を3つの視点で評価・分類する方法です。「Recency(直近の購入時期)」「Frequency(購入回数)」「Monetary(累計購入金額)」の頭文字が使われています。
顧客をランク別にグループ化することで、それぞれに適したアプローチが可能になります。一例として、過去に頻繁に購入していて最近は離れている層には、再購入に使えるクーポンの配布などが考えられます。既存顧客を維持・活性化させるうえで有効です。
アクセス解析
アクセス解析とは、Webサイトに訪問したユーザーの行動傾向や課題を可視化する手法です。ページごとの閲覧数や滞在時間、離脱ポイントなどの情報を分析し、Webサイトの状況や効果を把握します。
特定のページのみを見てサイトを離脱する直帰率が高い場合は、Webサイトの構成や導線に問題がある可能性があります。改善すべきポイントを明確にすることで、コンバージョン率の向上や回遊性の強化にもつながるでしょう。
アソシエーション分析
アソシエーション分析は、膨大なデータの中から項目同士の関連性を導き出す手法です。ある条件が満たされた時に、別の結果がどれくらいの確率で発生するかを明らかにします。
例えば「商品Aを買った人は、商品Bも一緒に購入している」というようなパターンが挙げられます。こうした発見は、クロスセルや商品陳列、レコメンド機能の精度向上に役立つでしょう。
クラスター分析
クラスター分析は、データの中から似た傾向を持つ要素をグループ化する手法です。性別や年齢などの明確な属性によるグループ分けではなく、行動傾向や趣味嗜好などに基づいて分類するのが特徴です。グループ数を決めないで分類する「階層型」と、あらかじめグループ数を決めて分類する「非階層型」があります。
グループの特徴を「ジャズファンで、コンサートによく行く」「クラシックファンで、自宅でCDを楽しむことが多い」など人の手で定義付けることで、グループごとに最適なアプローチを設計できます。
回帰分析
回帰分析は、ある要因(説明変数)が結果(目的変数)にどれだけ影響を与えるかを調べる統計的な手法です。例えば、気温が上がるとアイスクリームの売上も上がるといったことが挙げられます。複数の要因から一つの結果を導き出す手法もあり、顧客の購買行動の予測にも活用できます。
決定木分析
決定木分析は、ツリー構造で一定の基準ごとの影響を視覚的に整理し、顧客満足につながる要因を探る手法です。質問へのYes/Noや一定の条件に応じて枝分かれしながら、結論を導き出します。
例えば、ツリーの一番上に商品の購入率を置き、その次は年齢別の購入率に、さらにその次はキャンペーン中とそれ以外の場合の購入率へと枝分かれしていき、最終的にはどのような層の購入率が高いかを導き出すという流れです。
各条件の影響度が明確になり、商品表示の最適化や価格戦略の改善に活かすことができます。回帰分析よりも判断根拠が可視化されるため、意思決定の根拠を説明する際にも重宝される手法です。
データ分析・解析を行う際の注意点3つ
データ分析・解析を成功させるためには、事前に把握しておくべき注意点があります。ここでは、特に重要な3つのポイントについて詳しく解説します。
目的を明確にする必要がある
データ分析や解析に取り組む際、まず最初にすべきことは「何のためにデータを扱うのか」をはっきりさせることです。売上アップを目指すのか、顧客満足度の向上がゴールなのか、目的を明確にすることで、必要なデータや分析手法の選定、施策への展開がスムーズになります。
業務の負荷やコストがかかる
データ分析は、データの収集・整理・加工など手間と時間がかかります。業務負荷を軽減する手段としてツールの活用がありますが、ツールの導入や複数ツールを使いこなす人材育成にコストを割かなければなりません。特に原因を突き止めるデータ解析は、ツールのみでは不十分な場合があり、専門スキルを持った人材が必要になります。費用対効果を考えて、分析・解析に取り組むことが大切です。
▶︎あわせて読みたい:AIをマーケティング分析に活用する方法は?メリット、活用事例を解説
作業が属人化しやすい
データ分析・解析には一定のスキルや専門知識が求められるため、業務が特定の担当者に集中しやすく、作業が属人化する傾向があります。属人化が進むと、担当者の不在によって分析業務が滞ったり、情報共有が十分に行われなかったりするリスクが生じます。ツールを扱う人を増やすために使いやすくサポートが受けられるツールを導入したり、分析・解析結果をすぐに共有できる体制を作ったりする必要があるでしょう。
データ分析・解析のツールを活用した企業の成功事例
Meltwaterのソーシャルリスニング(クチコミ分析)ツールを導入した企業の成功事例をご紹介します。ソーシャルリスニングツールとは、SNSなどから自社に関する顧客の声を拾い上げて分析するツールのことです。実際の導入企業がどのようにデータを活用し、どんな効果を上げているか見ていきましょう。
▶︎あわせて読みたい:Meltwaterのお客さま事例
株式会社NTTドコモ
NTTドコモではPR施策の企画や評価を代理店任せにしており、自社でのデータ把握が難しい状況でした。そうした課題を受けて導入されたのが、Meltwaterのツールです。
ニュースやSNS上での自社の露出度、顧客の本音、競合の戦略などの把握がリアルタイムで可能となり、「dポイント経済圏」の施策の精度が高まりました。また、施策の効果をすぐに実感できることで社内には達成感とやりがいが広がり、心理面にもプラスの影響をもたらしています。
株式会社リコー
RICOH(リコー)では、アジア太平洋地域でのマーケティング活動において、SNSやPRの分析が国ごとに行われており、情報共有や市場理解に課題を抱えていました。
こうした状況を改善すべく導入されたのが、Meltwaterのツールです。SNS分析・競合調査・メディア対応を一元管理できる環境が整い、運用効率が大幅に向上しました。タイや香港など各国の担当者が、アジア太平洋地域全体の顧客の声をリアルタイムで共有できるようになり、営業やマーケティングの提案に一貫性が生まれています。
サッポロビール株式会社
サッポロビール株式会社では、自社のSNS投稿に対する顧客の反応はチェックしていたものの、長らくソーシャルリスニングが行われていませんでした。導入するにあたっては、ブランドごとの反応を知ることを目的の一つに掲げました。
そこで、Meltwaterのソーシャルリスニングツールである「Explore」と「Radarly」を導入します。その結果、ブランドごとの投稿内容やエンゲージメントの高い投稿者、新商品の発売時の反応などを把握できるようになりました。自社が伝えたいことが顧客に伝わっているかを確認することで、ブランドイメージのズレを防ぐのにも役立っています。
まとめ|分析と解析の違いを理解し戦略に差をつけよう
この記事では、データ分析と解析の違いや、主な手法、成功事例を紹介しました。
ビジネスの現場で成果を上げるためには、データの性質を正しく見極め、適切な方法で活用することが重要です。特に、膨大な情報やソーシャルメディアなどの各種メディアを対象とする場合、専用ツールを活用することで、精度と効率の両立が可能になります。
Meltwaterの分析支援ツールは、リアルタイムでのデータの可視化や競合比較など、戦略立案に役立つ情報を提供します。データ活用を加速させる第一歩として、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者:
宮崎桃(Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター)
国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム